ワインの教科書をそろそろ改善すべき?ワインの今は大きく変化している!
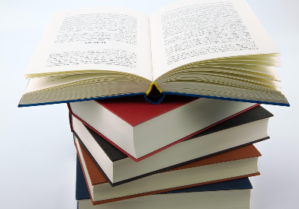
ワインに興味を持ち始めた方であれば、ワイン関連の資格を取得しようと考えるかもしれません。
飲食店に勤めていない方であってもワイン資格は用意されているため、多くの熱心な愛好家たちが資格取得に向けて日々勉強しているわけですが、ベースの内容もそろそろ変化させる時代にやってきているかもしれません。
ワイン業界の今を伝えなければ、間違った情報でワインが日本に広まってしまう可能性があるでしょう。その理由を考えていきます。
ワインの資格とは?
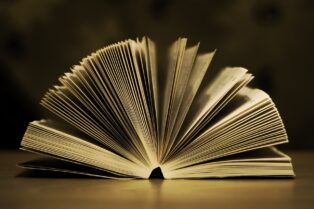
ワインを学ぶ上で、日本ソムリエ協会(JSA)が開催しているJ.S.A.ソムリエ・J.S.A.ワインエキスパートをベースにする方は多いでしょう。
飲食関連に従事している方であればソムリエを受験できますが、一般の方であればワインエキスパートを受験することが可能です。
これら日本ソムリエ協会(JSA)の提供する資格は大変難易度が高く、シニアソムリエの試験は針を小さな糸に通すような難問が出てくると言われています。
あまりにもマニアックな知識を勉強させるのも問題だと感じますが、それでもこの資格をとることで権威につながるといったかたちで毎年受験者が多いようです。
さて、そんなワイン資格の勉強で大切なことは、とにかくどの国のどの産地で、どんな品種やワインがつくられているのか暗記することでしょう。
また、簡単な法律や醸造テクニックなども勉強しなければなりませんし、国も増えています。ワインの管理や接客、料理とのペアリングなども含まれているようです。
テイスティング試験などがある2次、3次をクリアする前に、まずは徹底した座学が必要になります。
世界地図は変わっている
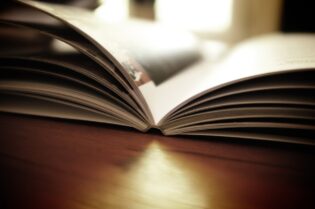
ここで問題なのが、細かい数字に変化はあるものの、ベースの情報は数十年前から変わっていないところです。
もちろん、AOPなどのベースは違うものの、ほぼ産地と品種の組み合わせ、何が有名かといった部分は一緒でしょう。
しかし、世界のワイン産地を見ると気候変動などの影響で、従来の栽培や醸造とは違ったようなものが生み出されています。
超有名産地であっても10年前とはワインの質が全く変わっていたり、主要品種も少しずつ変化が訪れているようです。
イギリスや中国、ブラジルといった新たな産地も増えてきており、もはや数十年前の問題構造とは違った現代版の新たな教科書づくりが必要になってきています。
基本を知ることは大切ですが、世界のリアルなワイン事情と乖離があっては現場で知識を使えません。
実際、10年以上前に資格を保有している方であっても、リアルな現場を見ると知らないことばかりだそうです。
そろそろ、全く新たな内容にワイン資格もアップデートする時がきています。
ナチュール系はどうするのか?
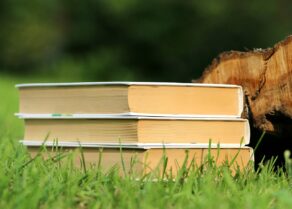
さらに問題として、近年トレンドになっているナチュール系はどう勉強すべきなのでしょうか。
これらワインは、オーガニック栽培やビオディナミ、減農薬などひとまず有機的な栽培と学べますし、そのアプローチを学ぶことはできるでしょう。
しかし、オフフレイバーをはじめ、欠陥なのかそうでないのか、そもそもアロマホイールでは出てこないような特異なニュアンスを持つワインばかりですので、味わいなどの定義がかなり難しくなります。
“マイノリティなワイン”といえばそうですが、もはや世界的トレンドであり、広く日本のワイン売り場でも入手できるようになっています。
もちろん、上記でお伝えした内容以外にも着目しなければならない、新たに加えなければならない情報は満載でしょう。
ワインの全てを網羅するといった学び方自体も、もはや難しくなってくるのではないでしょうか。


