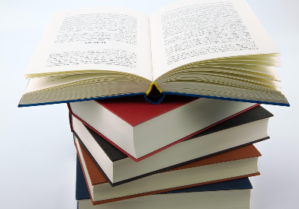料理とワインが同じ産地だとマリアージュ?時代は変わってきた!

ワインのペアリングテクニックとして知られているもののひとつに、産地を合わせるといったものがあります。
具体的には、その土地で生まれた料理であればその土地で生まれたワインと相性が良いはずといった内容で、その理屈を用いたペアリングは今でも推奨されているようです。
自宅でワインと食事のペアリングを楽しむ上でも、上記テクニックは活用できますが、注意しておきたい点もあります。
ワインと料理の産地を合わせる上で、注意しておきたいテクニックを解説します。
産地と料理を合わせる

料理とワインの産地を合わせるペアリングテクニックですが、基本的にワイン伝統国における理屈です。
ワインの資格試験を勉強された方であれば理解しているかもしれませんが、ボルドーのワインはどの料理に合わせるべき、ブルゴーニュであればこのワインを合わせるべきといったかたちで丸暗記させられる内容です。
ただし、この組み合わせは伝統的に伝えられてきているもので間違いではなく、実際に合わせることで素晴らしいマリアージュを楽しむことができます。
そのため、料理とワインを合わせる際、産地を意識したペアリングテクニックが推奨されており、近年ワイン新興国として知られるようになった国でも産地同士のペアリングが提案されているようです。
それしかなかった時代の名残

料理とワインを産地で合わせる際、大切になってくるのが、“その土地で古くからつくられていた料理とワイン”であるといった部分です。
フランス、イタリア、ドイツ、スペインなどは数千年前からワインがつくられており、一方で郷土料理も古くから地域で食べられていたものになります。
現代のように世界中のワインが手に入るわけでもなく、食材が自由に手に入るわけでもなく、当時は限られた食材でつくられた郷土料理とそれに合わせたワインがつくられていたといった背景があるでしょう。
日本で言えば、古くからその土地でつくられてきた日本酒と郷土料理は、現地の方が楽しむためにつくられていたものであり、酒も地域の味に寄せたようにつくられてきました。
海に近い街なので魚介類を使った郷土料理が生まれた、それに合うワインが必要であるため地元では魚介に合うようなワインがつくられてきた、このような流れで料理とワインにおける、“産地ペアリング”が構築されてきたと考えられるでしょう。
そこまで意識しないで良い?

一方、一部のワインは別として、わざわざ郷土料理に合わせたワインづくりをする生産者は少ないでしょう。
地元よりも外にワインを売らなければ経済的に成り立ちませんし、そもそもワインをその地元の方が日常的に飲んでいるかといえば微妙です。
とくに日本ワインの世界では、同じ産地の食材に大して同じ大地から生まれたもの同士共通点がある、その土地らしい方向性が合うといった具合でペアリングが提供されることもあります。
しかし、ソムリエの多くはそれはないと言いますし、科学的にもかなり曖昧で神秘的なペアリングとしか言いようがありません。
要するに、気持ちの問題です。
伝統国でも昔のようなスタイルでワインを醸さない生産者も増えてきており、同じ郷土だからといったペアリングに固執する時代でもなくなってきています。
料理側もどんどん洗練されモダンになってきていますし、それとこれは別。そう考える必要があるでしょう。
あくまで、郷土料理を愛し、その味に合わせてワインを醸すようなものがあればペアリングとしては成立するかもしれません。
ただ、同じ産地というだけで完璧なマリアージュは生まれない、そんな時代と考えたいところです。